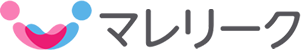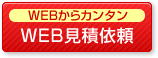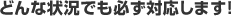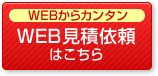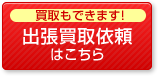相続税申告を考慮して財産を相続するか放棄するかは早めに検討しましょう。
- 2017/09/28
- お役立ち情報
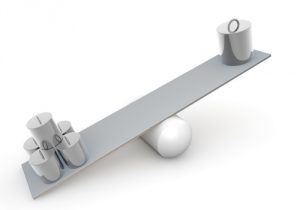
目次
- 相続財産をどうするか検討しましょう
- 財産は相続する?放棄する?どちらも手続きが必要
- 相続放棄は相続人全員に相談と承諾を!
- 相続税申告が必要なケースもある
- 相続放棄や相続税申告は必ず期限を守りましょう
- 事実婚や内縁の配偶者の場合
相続財産をどうするか検討しましょう
故人(被相続人)が残した財産には、現金や預貯金、株式などの有価証券、不動産や自動車などの「プラスの財産」や、住宅ローンの借入金、未払いの医療費や家賃、税金といった「マイナスの財産」があります。
財産相続は被相続人が亡くなられたからといって自動的に相続人に引き継がれるわけではありません。
相続するにもさまざまな手続きが必要となりますが、まずは財産にどのようなものがあるのかを調査して探し出し、財産の内容が把握(確定)できたら全体を整理して、相続することにょる影響をしっかりと見極めて相続するか放棄するかを判断する必要があります。
相続財産の金額や負債の有無によって、取るべき手続きが変わってきます。
それらの手続きには期限が決まっているものもありますので、被相続人が亡くなり相続が開始されたらすみやかに財産の内容を確認しましょう。

財産は相続する?放棄する?どちらも手続きが必要
「プラスの財産」が少なく「マイナスの財産」の方が大きいため相続したくない場合や、関与したくないという場合、財産を相続する権利や資格を捨てて行使しない選択をすることが可能です。
相続放棄の手続きを行った相続人は、法律上、財産を受け取る権利を失うことになり、最初から相続人ではなかったとみなされることになります。
放棄する財産は、「マイナスの財産」だけに限らず被相続人の財産(遺産)すべてが対象となるため、当然「プラスの財産」を相続する資格も失うことになります。
相続放棄が認められたあとは、いかなる理由があった場合でも相続放棄を撤回することができませんので慎重な判断が必要です。
これは民法で定められたルールであるため、やっぱり相続したいからと思い直したとしても、一度認可された相続放棄は撤回できません。
なお、相続の開始から相続放棄できるまでの期限は3か月です。
財産を相続するか、放棄するかについて検討する猶予は十分ありますので、相続財産に見落としがないように財産調査はしっかりと行いましょう。
相続を放棄する手続きは、故人(被相続人)の住民登録地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」や必要書類を揃えて提出し、申請します。
相続放棄は相続人全員に相談と承諾を!
相続放棄の前に最も慎重に検討しておかなければならないこと、それは自分が相続の権利や資格を放棄することで親兄弟に大きな影響を及ぼす可能性があるということです。
財産の相続が発生した場合には必ず相続人になる配偶者、第1順位の子、第2順位となる直系尊属(父母や祖父母など)、第3順位の兄弟姉妹というように法定相続人間においても順位が定められています。
先順位の方が相続放棄すると、次の順位の方が相続人になり、次の順位の方が相続放棄するとさらに次の順位の方へと相続権が移り変わっていくことになります。
優先順位にあたる相続人が相続放棄をした事実を知らずに、次の相続人となる親族がマイナスの財産を相続するようなことがあっては大変です。
今後の親族関係に悪影響を及ぼす原因にもなりますので、不要なトラブルを回避するためにも遺族や次順位の相続人に「相続放棄を考えている」という意思を伝えること、そして承諾を得ておくことは重要と言えます。

相続税申告が必要なケースもある
相続税は誰にでも生じるわけではなく、被相続人の財産が一定の金額を超える場合などに発生する税金です。
相続財産が基礎控除額を超える場合には、被相続人が死亡したときの住所地を管轄する税務署へ相続税を申告し、納税する必要があるので注意しましょう。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
財産を調査してどこにどんな財産があるかを把握できたら、相続税額を計算するために財産の価値を金銭で評価(財産評価)します。
相続財産の評価は、原則として相続開始日(被相続人が死亡した日)の時点で国税庁から公表されている「財産評価基本通達」とよばれる評価基準に従って行われます。
財産評価で財産の価値を把握した上で相続税を計算し、税務署に申告が必要かどうかできるだけ早いうちに確認するようにしましょう。
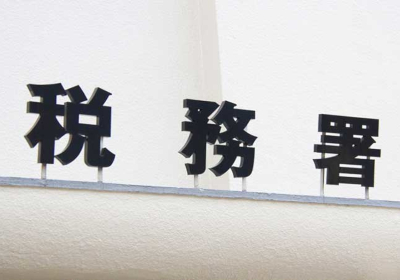
相続放棄や相続税申告は必ず期限を守りましょう
相続放棄の手続きや相続税の申告には期限が定められています。
決められた期限内に相続放棄の手続きをしなければ、マイナスの財産を切り捨てることができなくなりますし、相続税を決められた期限内に正しく申告し、納税をしなかった場合には延滞税などさまざまなペナルティーが科せられてしまいます。
相続放棄や相続税申告など期限がある手続きの必要性が想定されるような場合は、期限に余裕をもって行うようにしましょう。

事実婚や内縁の配偶者の場合
事実婚や内縁とは、結婚しているという意思のもと実質的には夫婦関係にありながら、婚姻の届出をしていない(未入籍)状態であるため、法律上の夫婦とは認められていない関係のことです。
事実婚や内縁といった法的な婚姻関係にない配偶者に、法律上の相続権はありません。
亡くなった方(被相続人)が法的効力を持つ遺言などに事実婚や内縁の配偶者に対する相続の意思を書き記していなければ、法的な婚姻関係にない方に相続権が生じることはありませんし、税金の優遇を受けることもできません。
法律婚(戸籍上・法律上)の夫婦以上に、事実婚や内縁の関係にある夫婦は財産相続にそなえて然るべき対策を取っておく必要があると言えるでしょう。
もしすべての相続人が相続放棄をするなど法律上の相続人が存在しないという場合や、期限内に相続人が名乗り出なかった場合、最終的に相続財産は国の保有となり国庫に帰属することになりますが、事実婚や内縁の配偶者が「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」として家庭裁判所に対して「相続財産の分与請求」をすることも可能です。
特別縁故者とは、被相続人に法定相続人がいない場合、特別に相続を受ける権利が発生した方のことをいいます。
事実婚や内縁の配偶者など被相続人と生計を同じくしていた方以外に、被相続人の療養や看護に努めた方や法人なども「特別縁故者」の対象となります。
ただし、特別縁故者と認められるためには、民法958条の3第1項に定められた条件のうちのどれかに当てはまらなければならないとされています。
| 特別縁故者の条件 |
|

あわせて読みたい関連記事