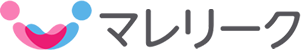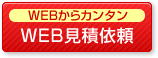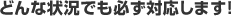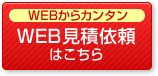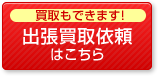遺産分割調停の申立ては財産相続の問題を解決するひとつの方法
- 2017/10/05
- お役立ち情報

目次
遺産分割協議で財産の分け方が決まらないこともある
被相続人が作成した法的に有効な「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」などが残されていた場合、遺産分割方法の指定が記載されていればその遺言内容に従って相続手続きを進めるのが原則です。
一方、有効な遺言が存在しない場合には、相続放棄した方以外の相続人全員で「遺産分割協議」を行い、財産の分け方を話し合いで決める必要があります。
遺産分割協議とは、現金や銀行預金、土地や建物などの相続財産のうち「誰」が「どの財産」を「どれくらいもらうか」について相続人同士で決定する話し合いのことを言います。
では、もしも相続人同士の話し合いで全員の合意に至らなかったり、協議の参加を拒絶する相続人がいるなどの事情によって相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立しない(財産の分け方が決まらない)場合、どうすればいいのでしょうか。
遺産分割協議では互いの利害が衝突し合うことも多く、仲の良い親族同士でも話し合いがまとまらず何年経っても決着がつかないケースは少なくありません。
相続人の中には長く疎遠になっていたため連絡が取れない方や、面識がなく連絡先がわからないということもあるでしょう。
いずれにしても、遺産分割協議は相続人全員で話し合いを行った上で、相続財産の分割方法について相続人全員が合意する必要があり、たとえ一人でも不参加であったり対立する意見の相続人がいた場合には遺産分割は無効となるので、遺産分割の解決方法を変えなければいけません。
相続人だけで行う遺産分割協議で財産の分け方が決められないのであれば、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
つまり、家庭裁判所の介入によって財産分割の解決を図るという手続きをするということになります。

遺産分割調停が解決の第一歩
遺産分割協議が不調の場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停の申立て」を行うことができます。
調停は裁判所で行う手続きとなりますが、基本的には裁判官と調停委員で構成される調停委員会が仲介となって相続人間の合意を成立させるための「話し合い」であることに変わりはありません。
とはいえ、相続人だけで収拾をつけることが困難な話し合いに、円滑に自主的解決できるよう手助けしてくれる中立公正な第三者が介入することで、財産分割の合意に至りやすくなります。
遺産分割調停は、「共同相続人」「包括受遺者」「相続分譲受人」に該当する方が申立人となり、他の相続人全員を相手方として申し立てることができます。
白黒はっきりさせるいわゆる「裁判」とは違い、遺産分割調停では調停委員会が相続人全員からそれぞれの事情や財産分割に対する意向を平等に聴取し、提出された相続人や相続財産に関する資料をもとに解決に向けて必要な助言や説得を行い、法律の枠組みにかなった合意を目指した話し合いが進められることになります。
遺産分割調停の申立て手続きの方法
遺産分割調停の申立て手続きでは、遺産分割調停申立書をはじめとするさまざまな関連資料を提出する必要があります。
| 申立人 |
|
| 申立先 |
|
相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所 |
| 必要書類 |
|
| 手数料 |
|

遺産分割調停の流れ
遺産分割調停の申立てが受理されると、家庭裁判所から相手方の相続人全員に対して「調停期日の通知書」「申立書の写し」「進行に関する照会回答書」などが送付され、申立人と相手方の相続人は家庭裁判所から指定された調停期日に裁判所へ集まり調停を行うという流れになります。
調停は1か月に1回ほどのペースで開かれますが、最低でも4~5回程度行われるのが一般的となっており、財産分割の結果がまとまるまで通常1年程度、場合によっては2年以上かかることもあります。
調停はあくまでも双方の合意による解決ですので、申立人と相手方がいずれも納得した場合に「調停が成立」となり、遺産分割調停は終了ということになりますが、合意が成立しない場合には「調停が不成立」となります。
また、相続財産の分割方法を話し合う期間に決められた制限はありませんが、相続税の申告・納税が必要な場合は期日に注意しなければいけません。
相続する財産が基礎控除額を超える場合には、被相続人の死亡日(相続の開始日)の翌日から10か月以内に相続税の申告・納税を済ませる必要があります。
相続税の申告・納期日を超えた場合、各種控除や特例が利用できないだけでなく、場合によっては追徴税(延滞税や加算税)といったペナルティが料される可能性がありますので、期日を超えて調停が長引くことがないようにすることが最優先です。
- 関連記事:相続税の基本について覚えておきたいこと

調停では基本的に当事者間で話し合うことはありません
調停が不成立の場合、審判で財産分割の方法を決める
遺産分割調停が不成立になった場合には、自動的に「遺産分割審判」の手続きが開始されることになり、法律に従って裁判所が遺産分割の方法について判断を示すことになります。
遺産分割審判は、訴訟(裁判)のように各当事者の主張や提出された証拠資料からあらゆる事情を考慮した上で、民法第906条「遺産の分割の基準」 に基づき財産の分割方法を決める手続きです。
遺産分割「審判」は遺産分割「調停」と同じく家庭裁判所で行う手続きではありますが、「話し合い」である調停に対して審判は「強制的な決定」を下す方法であるという明確な違いがあり、裁判所による決定には強制力があるため、申立人と相手方は双方ともに下された結果に従わなければなりません。
相続人である当事者同士が話し合う「遺産分割協議」や第三者の仲介による「遺産分割調停」で、財産の分割方法を決めるのが最も望ましいですが、「遺産分割審判」は意見の対立などによって解決が難しい場合の最終手段と考えましょう。
遺産分割協議から調停、審判へと移行してきた場合、遺産分割の確定まで相続トラブルが長期化することも考えられます。
相続人間の合意ではなく法的な主張と立証に基づいた決定(判決)で行われる「審判」では、必ずしも当事者の意向に沿った希望通りの結果になるとは限りませんし、納得できない結論が出る可能性もあり、相続人同士の関係性を改善するのもより難しくなると予想できるでしょう。
将来的に財産相続で争いになることは避けたいもの。
いつか相続人や遺族となる大切な方々のためにも、生前整理で身辺整理をしておいたり遺言を残しておくことの重要性をあらためて知っておくことは大切ですね。
- 関連記事:遺品整理に活かす生前整理

あわせて読みたい関連記事